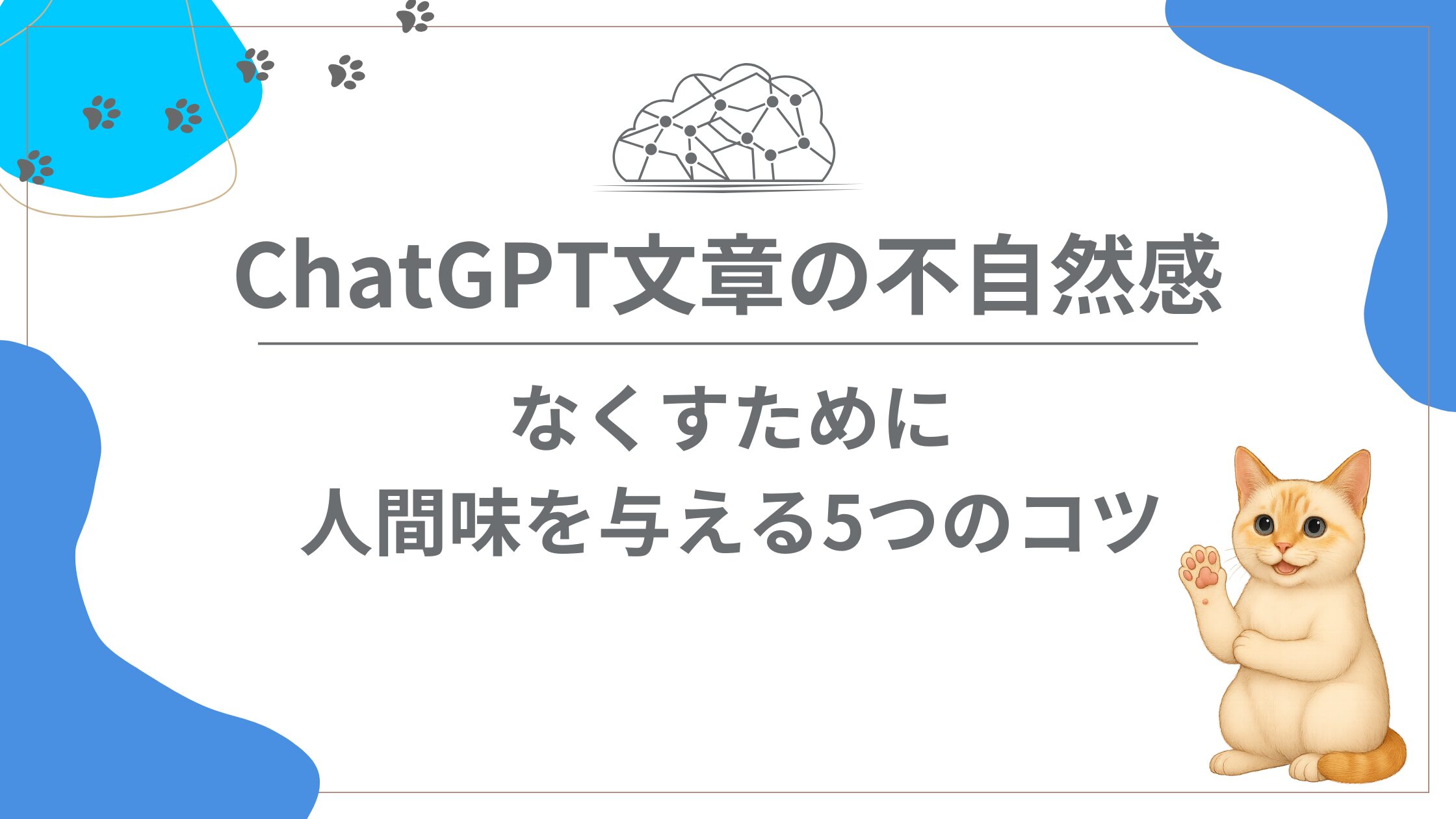ChatGPTで文章を作ると、内容は整っているのに「人の言葉らしさが足りない」と感じることはありませんか。
今回は、前回の“依頼文で作る”から一歩進めて、“必要なときに一つだけ取り入れれば十分”という考え方で、人間味を補うコツを紹介します。
まずは、整いすぎた文に小さな揺らぎを戻すところから始めてみましょう。
コツ①:整いすぎた文に“揺らぎ”を戻す
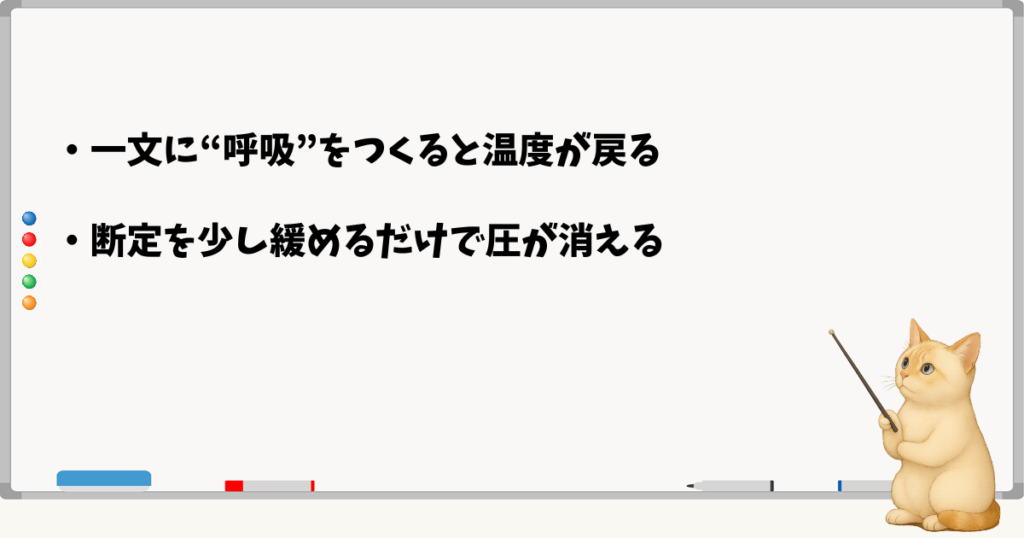
ChatGPTが書く文章は正確で丁寧。それだけに、読みやすさの裏で「温度がない」「距離を感じる」と思われることがあります。
これは、文が整いすぎて“人の呼吸”が消えているからです。
このコツでは、内容を変えずにほんの少し崩して、自然な揺らぎを戻す方法を紹介します。
一文に“呼吸”をつくると温度が戻る
AIが作る文は、文末も敬語もきれいに整いすぎる傾向があります。 その結果、正しいのに「事務的」「冷たい」と感じられるのです。 特に、敬語の層が厚く定型句が続くとAI的な硬さが目立ちます。
ダメな例:
「ご協力いただき誠にありがとうございます。引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げます。」
整え例:
「ご協力ありがとうございます。大変助かりました。引き続きよろしくお願いします。」
意味は同じでも、余分な敬語を一段階減らすだけでぐっと自然になります。
人の文は「息づかいの間」があるから温度が伝わります。 ChatGPTで文章を直すときは、“意味は変えずに会話のリズムを加えて”と伝えると良いでしょう。
たとえば依頼時に「次の文を話しかけるようなリズムで整えてください」と添えるだけでも出力が変わります。
断定を少し緩めるだけで圧が消える
AI文章のもう一つの特徴はすべてが言い切り調になることです。
「〜です」「〜します」が続くと、内容は正しくても圧を感じる。 そんなときは、補足部分をやわらげて“余白”をつくります。
ダメな例:
「見積書を本日中に提出してください。社内決裁に必要です。遅延は避けてください。」
整え例:
「見積書は本日中にご提出ください。社内決裁の都合で今日だと助かります。もし難しい場合はご連絡ください。」
要請はそのままに、理由と代替の余地を加えることで自然な“人の余裕”が生まれます。 このときもすべての文を緩める必要はありません。
要件は端的に補足だけやわらかく。 核心と補足の温度差を意識することで、文章全体のバランスが整います。
使いどころ: 依頼や報告など、“伝わること”が目的の文書に最適です。 逆に契約書や通達のような公式文では、曖昧さを避けて正確さを優先しましょう。
まとめ: 整いすぎた文は、ほんの少しの呼吸と余白で印象が変わります。 文の中にひとつだけ“緩む場所”をつくる——それだけで、読み手が感じる温度は大きく違ってきます。
コツ②:テンポを変えて“呼吸のある文章”にする
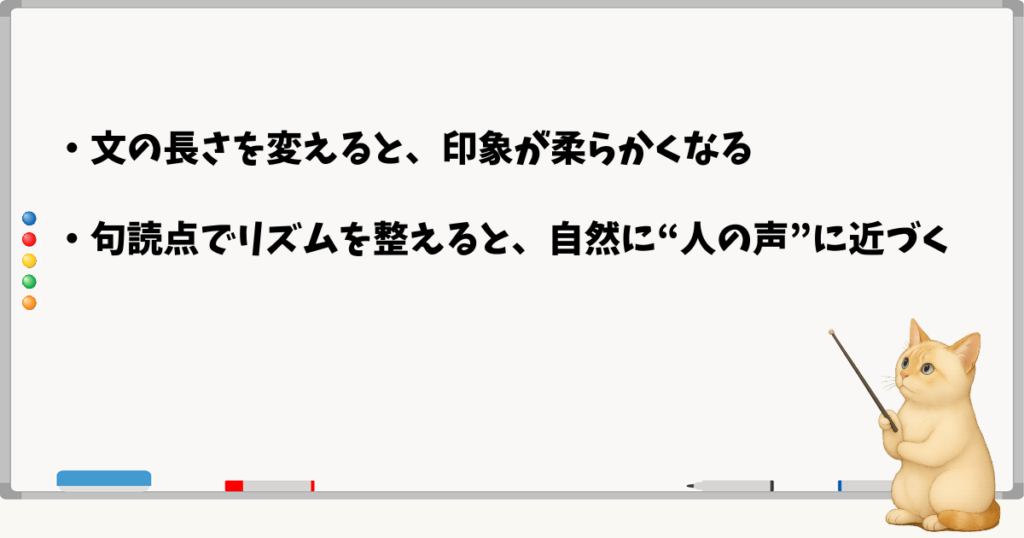
ChatGPTの文章は文法が正確で整っています。 しかし、その“整いすぎ”が原因で、読み手には「息が詰まる」「全部同じ調子」と感じられることがあります。
このコツでは、句読点と文の長さを変えて、読みやすさよりも“呼吸のしやすさ”を意識する方法を紹介します。
文の長さを変えると、印象が柔らかくなる
AIは構文を均等に組み立てるため、どの文も同じリズムになりがちです。
報告書や案内文などで、「〜します。〜します。」と続くと内容は理解しやすくても単調さが残ります。 そんなときは、文の長さを意識的にずらすだけで、読み心地が一気に変わります。
ダメな例:
「本日の会議では今後の方針を確認しました。次回は具体的な実施計画を共有します。担当者の割り振りを行います。」
整え例:
「本日の会議では、今後の方針を確認しました。
次回は、実施計画を共有する予定です。
担当者の割り振りについては、まず概要を整理してから進めます。」
「〜します。」を連続させず、途中に補足を入れるだけでテンポに変化が出ます。
文を短くすることよりも、“流れの途中に呼吸を置く”意識が大切です。
ChatGPTで修正を頼む場合は、「文の意味はそのままで、リズムが出るように整えてください」と指示するとよいでしょう。
句読点でリズムを整えると、自然に“人の声”に近づく
AIの出力は読点(、)が少なく、文が詰まった印象になりやすい傾向があります。
特にメール文や依頼文では一文が長いと「冷たく」「説明的」に感じられます。 読点を一つ加えるだけでも、印象は大きく変わります。
ダメな例:
「お忙しいところ恐縮ですがご確認のうえご返信いただけますと幸いです。」
整え例:
「お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のうえ、ご返信いただけますと幸いです。」
小さな変化ですが、読み手の中で“声に出せるリズム”が生まれます。 句読点は単なる区切りではなく、文章の呼吸を整える道具です。 ChatGPTに依頼する際も、「自然に声に出して読める文に直してください」と添えると、出力が穏やかになります。
使いどころ: 社内報告や依頼メール、顧客向け案内など、“情報を伝える文”で効果的です。 逆に契約文やプレスリリースなど、厳密な文体が求められる文章では、一定のテンポを保ちましょう。
まとめ: AIが作る文に“呼吸”を足すと人が読む速度に寄り添えます。 短文と中長文を混ぜ、句読点でリズムを調える。 それだけで整いすぎた文に人の声が戻ります。
コツ③:説明を“思考の流れ”に並べ替える
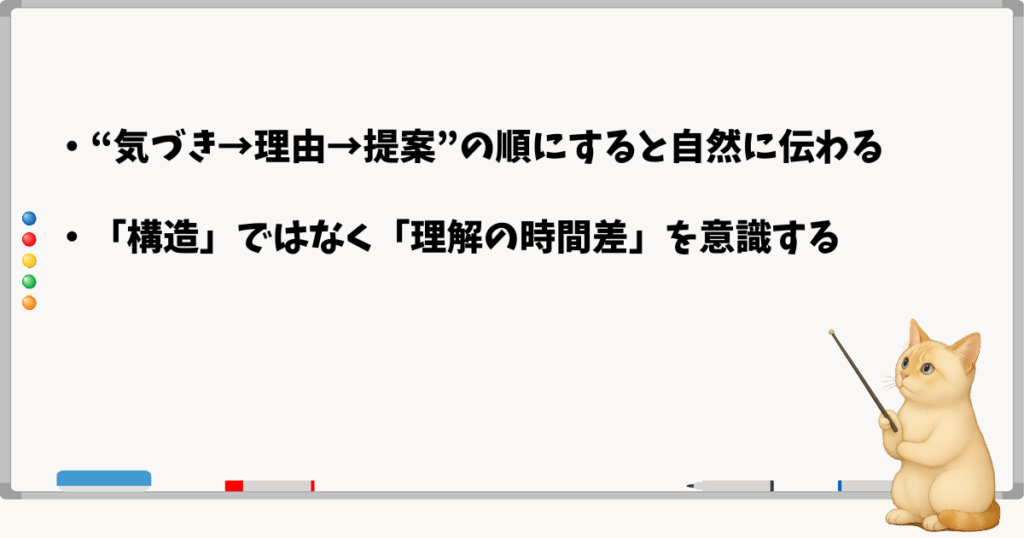
ChatGPTの説明文は論理的で正確です。 しかし、そのまま使うと「情報は多いのに、頭に入ってこない」と感じることがあります。
原因は、AIが“構文上の正しさ”を優先し、人が理解しやすい順番で組み立てていないからです。
ここでは、「説明の順番」を“読み手の思考の流れ”に合わせて入れ替える方法を紹介します。
“気づき→理由→提案”の順にすると自然に伝わる
AIは「結論→理由→補足」の構造を好みます。 ただし、読者がまだ内容に関心を持っていない段階で結論を先に読むと、「唐突」「理解が追いつかない」と感じます。
特に社内報告や提案文では、“気づき”を先に示すことで共感を引き出しやすくなります。
ダメな例:
「営業データの分析により、訪問頻度の高い顧客ほど受注率が高いことが分かりました。したがって、訪問回数を増やす施策を検討します。」
整え例:
「最近、訪問頻度の高い顧客ほど受注率が高い傾向があります。
データを分析した結果、その差は約1.8倍でした。
このため、次の施策では“訪問回数”を増やす方向で検討します。」
同じ情報でも、“読者の理解プロセス”に合わせて順を入れ替えるだけで伝わり方が変わります。 先に気づきを提示し、「なぜそうなのか」「だからどうするか」の順で続けると、読み手の頭の中で自然に整理されます。
「構造」ではなく「理解の時間差」を意識する
AIの文章はすべての要素を一度に提示する傾向があります。 しかし、人が読むときは「気づく→理解する→納得する」という時間差で処理しています。
そのため、文中に「間」を置くように段階を分けると、読み手の思考速度と合いやすくなります。
ChatGPTへの頼み方(例): 「次の説明文を“読者が納得しやすい順”に並べ替えてください。気づき→理由→提案の流れにしてください。」 このように指示すると、AIの論理構造が“人の理解構造”へと変わります。
使いどころ: 報告書・提案書・企画概要など、相手に理解と納得を促したい場面。 一方で契約書や議事録など、順序の厳密性が重視される文書では適用を控えます。
まとめ: AIが作る“正しい順番”を人が読む“自然な順番”に変える。 それだけで、説明文はぐっと理解されやすくなります。
コツ④:感情語ではなく“理由”で温度を出す
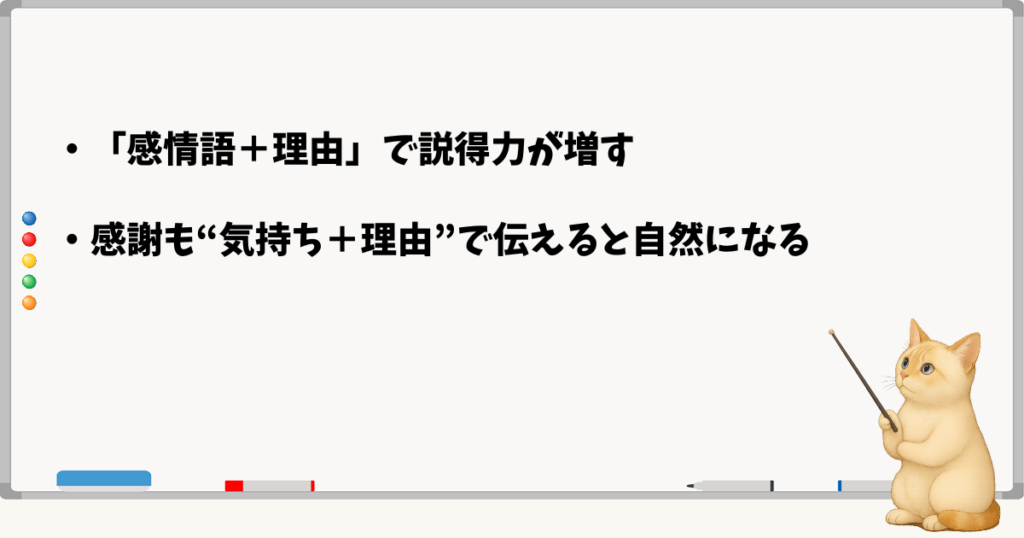
ChatGPTが書く文は感情語を多用する傾向があります。 「とても素晴らしいです」「本当に嬉しいです」──言葉としては温かいのに、なぜか軽く感じる。 それは、感情だけを伝えて“理由”がないためです。
人は「なぜそう思うのか」があるときに、相手の感情を信じやすくなります。
「感情語+理由」で説得力が増す
AIは学習上、ポジティブ表現を好みます。 しかし「嬉しい」「すごい」といった単語は、感情の“音”を伝えるだけで文脈を伴いません。 このとき、感情を理由で支えるだけで温度が伝わるようになります。
ダメな例:
「本日のプレゼンはとても素晴らしかったです!皆さんの努力に感動しました!」
整え例:
「本日のプレゼン、とても良かったです。特に事例の紹介が具体的で聞き手の理解が深まりました。」
感情語を一つ残し、「なぜ良かったのか」を加えるだけで印象がまったく変わります。 “感動した”という主観を相手の行動や成果に結びつけて具体化する。 これが「AI的なお世辞」から「人の評価」へ変えるポイントです。
感謝も“気持ち+理由”で伝えると自然になる
AIは「感謝」を表す表現も少し硬くなりがちです。 「誠にありがとうございます」「感謝申し上げます」などが並ぶと、正しいけれど温度が感じにくい。 そんなときは、感謝の“理由”を一言添えるだけで十分です。
ダメな例:
「このたびはご対応いただき誠にありがとうございました。」
整え例:
「このたびはご対応ありがとうございました。おかげで日程がスムーズに調整できました。」
感謝の理由を添えることで、読み手は「この人はちゃんと見てくれている」と感じます。 ChatGPTに依頼するときは、「お礼文を“なぜ感謝しているのか”が伝わる形にしてください」と伝えると良いでしょう。
使いどころ: お礼メール、成果報告、評価コメントなど、“良かった”を伝える場面に適しています。 一方で、公式声明や謝罪文のように感情を控える必要がある文書では避けましょう。
まとめ: 感情を直接書くより、“理由で温度を出す”方が誠実に伝わります。 嬉しい・すごいではなく、なぜそう感じたのか。 一言の理由が文章に人の信頼を取り戻します。
コツ⑤:言葉の“距離感”を整える
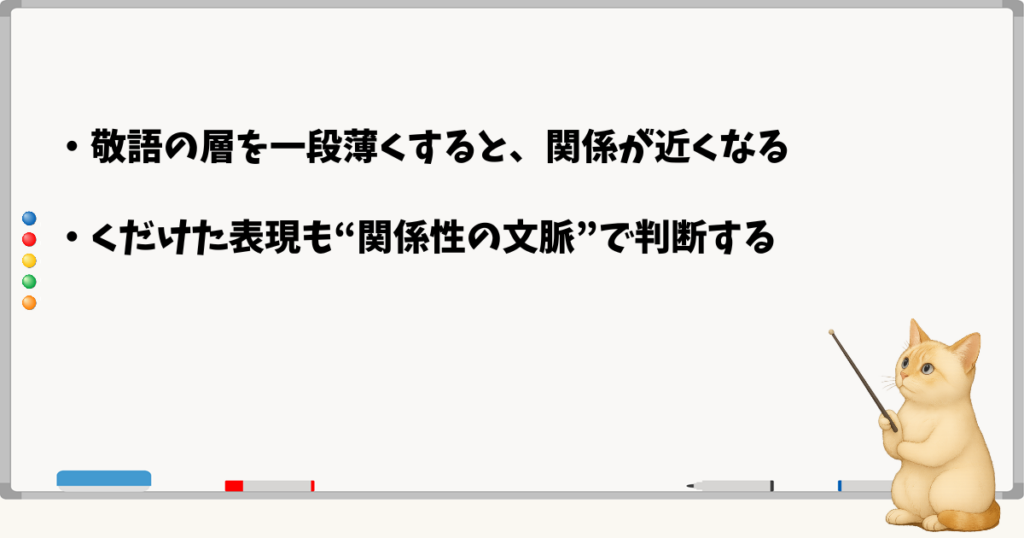
ChatGPTが書く文章は礼儀正しく安全です。 そのため、ビジネス文書として誤りはありませんが、読んだ相手には「少しかしこまりすぎ」「距離がある」と感じられることがあります。
一方で、トーンを崩しすぎると軽く見える。 自然な文に整えるには、相手との関係に合わせて“丁寧さの層”を一段だけ調整することがポイントです。
敬語の層を一段薄くすると、関係が近くなる
AIは安全策として最も丁寧な敬語レイヤーを採用します。 たとえば「ご教示賜りますようお願い申し上げます」「ご多忙のところ恐縮ですが〜」など。
これらは間違いではありませんが、やや重たく、日常的なやり取りには堅すぎる印象を与えます。
ダメな例:
「ご多忙のところ恐縮ですが、仕様書のご送付につきましてご対応賜れますと幸いに存じます。」
整え例:
「お忙しいところ恐れ入ります。仕様書の送付をお願いできますか。」
意味は同じでも敬語の層を一段薄くするだけで、相手が受け取る圧が和らぎます。 また、「〜賜ります」「〜申し上げます」といった二重敬語を避けると、読み手の理解スピードも上がります。
ChatGPTで依頼する際は、「次の文を、取引3年目の担当者に送るメールとして自然に整えてください」と前提を添えると良いでしょう。
くだけた表現も“関係性の文脈”で判断する
一方で、社内メールやチャットでは、少し柔らかい言い回しの方が自然なこともあります。 ただし、フレンドリーと軽率は違います。 “関係性に合う柔らかさ”を意識すると、トーンがぶれずに済みます。
ダメな例:
「お疲れさまです!例の件どうなってますか?」
整え例:
「お疲れさまです。例の件、進捗いかがでしょうか?」
たった一語の違いでも印象は大きく変わります。 チャットのテンポ感を保ちながら、文末の整え方だけで“落ち着きのある親しさ”が生まれます。 トーンを整えるときは、「相手が自分の立場で読んだらどう感じるか」を一度想像するのが最も効果的です。
使いどころ: 取引先への日常連絡、社内の報告・相談、プロジェクトメンバーとのやり取りなど、“言葉の温度”が成果につながる場面。 一方で契約締結や公式文書など、記録性が重視される場ではこの調整は不要です。
まとめ: AIの文は「正しいけれど遠い」。 相手との関係性に合わせて敬語を一段薄くする、あるいは言葉の温度を半歩上げる。 それだけで、読み手との距離が自然に近づきます。
まとめ:ChatGPTの文章を“人の言葉”に戻すという考え方
ChatGPTが生み出す文章は正確で整っています。 しかし、整いすぎた文はときに、伝えたい気持ちや人の温度を薄めてしまいます。
今回紹介した5つのコツ──「揺らぎ」「呼吸」「思考の流れ」「理由」「距離感」──は、 すべてを使うためのものではありません。
自分の文に違和感を覚えたとき、“どれかひとつ”を試してみる。 それだけで、AIの文はぐっと自然に変わります。
大切なのはAIを“自動化の道具”としてではなく、人の伝え方を見直す鏡として使うことです。 ChatGPTが整えた文章を、もう一度人の目で読み返し、息づかいや温度を戻す。 その繰り返しが、AIと共に「伝わる表現」を育てていく第一歩になります。
最後に、社内メールや報告書、提案文などで「AIの文が少し硬い」「どう直すと自然か迷う」と感じたときは、 無理に自分だけで抱え込まず、身近な視点を交えて確かめてみてください。 私たちCreamCodeでも、そうした“整え方の悩み”を一緒に考えるお手伝いをしています。
文章を直すことは伝えたい気持ちを整えること。 ChatGPTの力を借りながら、あなたらしい言葉を取り戻していきましょう。