「ChatGPTを使ってメールを作りたいけれど、どんなふうに頼めば自然な文章になるのか分からない」——最近、相談や打ち合わせでも、こうした悩みを耳にすることが増えました。
実際、AIにそのまま「お礼メールを書いて」と指示しても、どこか硬すぎたり、逆にくだけすぎたりすることがあります。
少しの工夫で、より自然で伝わりやすいメールを作ることはできますが、その“頼み方”のコツをつかめていない方が多いようです。
この記事では、ChatGPTにビジネスメールを作ってもらうときに役立つ「依頼文(プロンプト)」と「生成文(メール)」のペア実例を紹介します。
まずは、AIに書かせる前の準備——つまり、メールの内容をどう整理しておくかから見ていきましょう。
ChatGPTに依頼する前にまとめておきたい「メール内容の設計図」
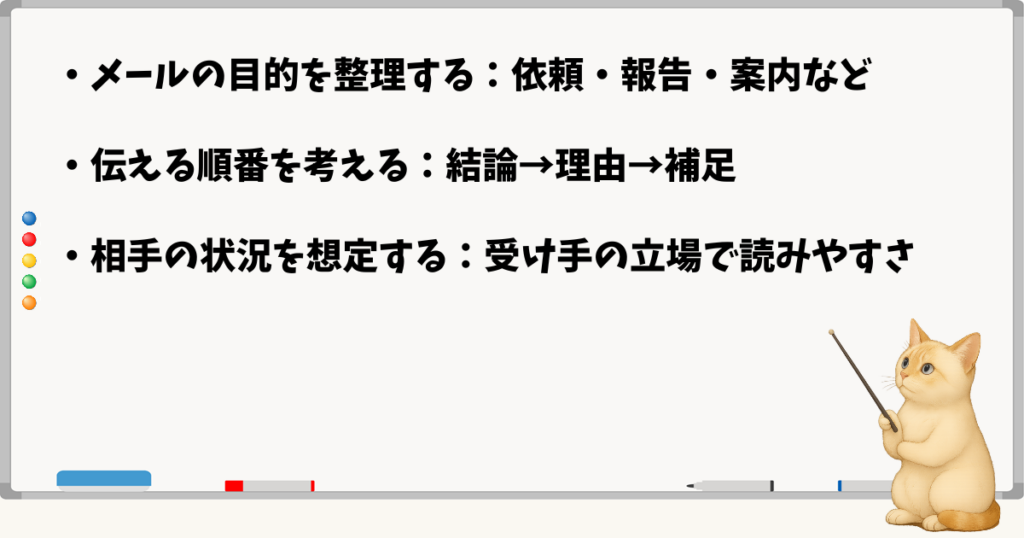
メールの目的を整理する:依頼・報告・案内などを明確にする
まず整理したいのは、「このメールで何を伝えたいのか」という目的です。
AIに文章を作らせる前に自分の中で目的をはっきりさせておくことで、出力の方向性が安定します。
たとえば「依頼したい」「お礼を伝えたい」「進捗を報告したい」など、ひと言で言える目的を決めておくと良いでしょう。
ChatGPTは入力された目的をもとに文章の構成や言葉づかいを判断します。
目的があいまいだとAIは安全な言い回しを選びがちで、結果として印象が薄い文になりやすいのです。逆に「お礼と再提案を両方伝えたい」など、複数の意図がある場合はどちらを主に据えるかを自分で決めておくことが大切です。
目的を整理する段階ではまだ文章にしなくて構いません。箇条書きで
「誰に」
「何を」
「どんな気持ちで伝えたいか」
を書き出すだけでも、AIに頼む際のブレが減り、自然な文が生成されやすくなります。
伝える順番を考える:結論→理由→補足の流れを決める
次に意識したいのは「伝える順番」です。
ChatGPTは指示どおりの順序で文章を構成しますが、こちらが意図する流れを伝えなければ、文全体の印象が散漫になってしまいます。
基本的には「結論→理由→補足」の順番を意識すると、どのようなビジネス文でも安定します。
たとえば、社外向けの依頼メールなら「お願いしたい内容(結論)」を先に置き、その理由や背景を短く添えると相手にとって読みやすい構成になります。
ChatGPTに依頼する前にこの“流れ”を自分の中でイメージしておくことで、AIに対しても明確な構成指示が出せるようになります。
また、社内向けの報告メールでは、逆に「背景→結論→次の行動」という流れが自然な場合もあります。
目的と相手の関係によって順序を調整する意識を持つと、より現実的な出力に近づきます。
相手の状況を想定する:受け手の立場から読みやすさを考える
最後に、「このメールを受け取る相手が、どんな状況で読むか」を想像してみてください。
ChatGPTに文を作らせるとき、この“受け手の前提”が抜けていると、形式的で温度のない文章が出やすくなります。初取引の相手なのかいつもやり取りしている取引先なのかによって、語調も表現も変わるはずです。
相手の立場を想定しておくと、プロンプトに「取引2回目の相手へ」「社内の上司へ」などの一言を添えられます。この情報があるだけでChatGPTは文体を自動で調整してくれるため、出力の精度が大きく上がります。
AIは、文脈を与えられた範囲で最適解を出す道具です。
相手がどんな人か、どんな状況かを整理しておくことは、メール全体の自然さを決める重要な前準備なのです。
ChatGPTに正確に伝えるためのプロンプト(依頼文)の書き方
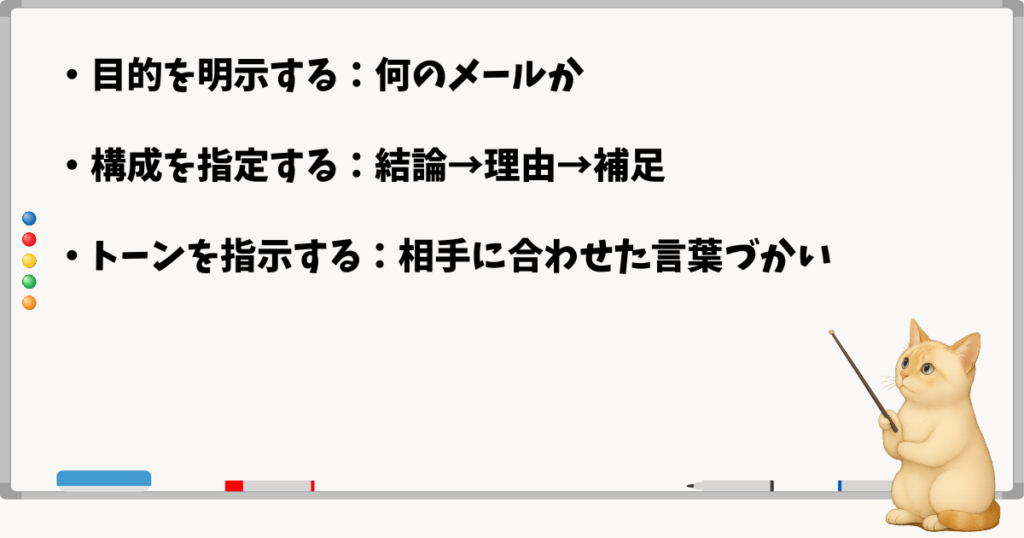
目的を明示する:何のメールかを最初に伝える
ChatGPTに依頼文を入力するときは、まず「このメールは何のためのものか」をはっきり示すことが大切です。
AIは目的の文脈を理解して文章構成を決めるため、ここがあいまいだと出力全体がぼんやりしてしまいます。
最初の一文に「取引先へのお礼メール」「社内の報告メール」「依頼を伝えるメール」など、用途を明示しましょう。
たとえば、単に「お礼メールを書いてください」と指示するのではなく、「取引先に初回打ち合わせ後のお礼メールを書いてください」と入力するだけで、語調や構成が自然になります。
AIは「初回」「取引先」「お礼」という情報をもとに、丁寧かつビジネスらしい文体を選択するからです。
また、複数の目的を同時に含む場合(例:お礼+提案、報告+確認など)は、どちらを主目的にするかを明示すると良いでしょう。「まずお礼を伝え、最後に次回の提案につなげたい」というように順序を指定すれば、AIはそれを踏まえて自然な流れを作ります。
目的の明示はAIへの「方向づけ」です。目的を短く、冒頭に書く。これだけで、生成される文章の安定感は大きく変わります。
構成を指定する:結論→理由→補足の順に書くよう伝える
次に、メールの構成をあらかじめ指定することが重要です。
ChatGPTは何も指示しないと一般的な文章構成を自動で採用しますが、それがあなたの意図と一致するとは限りません。構成を指示することで、意図した順序で情報が整理され、相手に伝わりやすい文になります。
依頼メールなら「最初にお願いしたい内容を述べ、その理由と背景を続け、最後にお礼を添えてください」と伝えます。報告メールなら「結果→経過→今後の対応」の順序で構成を指示します。
ChatGPTは“順番の言葉”を読み取ると、その構造どおりに文章を組み立てます。
もし書き出しが堅い場合は、「冒頭で一文のあいさつを入れてから結論を書いてください」と補足を加えると、より自然な印象になります。
AIはテンプレート的に動くため、構成指示を細かく入れるほど再現性が高まるのが特徴です。
この段階でのコツは、「どの部分を主に伝えたいのか」を明確にすること。AIにすべて任せるのではなく、文章の骨格をこちらで設計し、AIに肉付けさせるという考え方が最も安定します。
トーンを指示する:社外・社内など相手に合わせた言葉づかいを伝える
最後に、メールのトーン(口調・語調)を具体的に指示することです。
ChatGPTは状況の想定ができないと、一般的で中立的な文体を出します。
そのため、相手や場面に合わせて「丁寧」「親しみやすく」「やわらかく」「簡潔に」などの指示を入れることで、自然な仕上がりになります。
「社内の上司に報告するメールを、簡潔で落ち着いた口調で書いてください」「取引先への依頼メールを、失礼にならない丁寧語で書いてください」といった具合です。
調指定を入れるだけで、表現の過不足が抑えられ、手直しの手間が減ります。
さらに、「300文字以内で」や「3段落で」といった分量の指示を加えると、読みやすさが安定します。AIは情報量が多いほど文を冗長にしがちなので、あらかじめ長さの基準を与えると、端的で要領のよいメールが生成されます。
AIに“どう書かせるか”の鍵は、このトーン指示にあります。トーンは単なる雰囲気ではなく、相手への配慮を言葉で伝える技術。
その意識を持つだけで、ChatGPTはあなたの意図をより的確に反映してくれるでしょう。
シーン別・依頼文と生成結果でわかるメール文例集
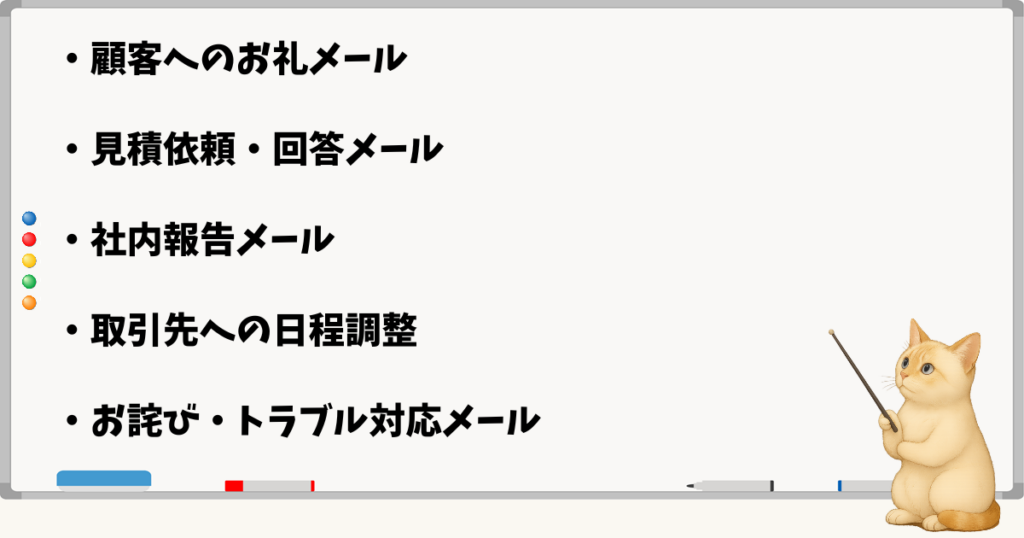
ここからは、これまで整理してきた考え方とプロンプト設計を踏まえ、実際にChatGPTに作らせたメール文例を紹介します。
依頼文(プロンプト)と生成結果をセットで見比べることで、どんな指示がどんな表現につながるかが分かります。自分の業務に近いシーンを参考にしながら、どんな伝え方が効果的かをつかんでみてください。
顧客へのお礼メール:感謝を伝える依頼文と自然な出力例
[依頼文(プロンプト)]
「取引先に初めて訪問したあとに送るお礼メールを書いてください。こちらの説明を丁寧に聞いてもらったことへの感謝を伝え、次回の提案につなげたいです。200文字以内でお願いします。」
[ChatGPTの生成結果]
「本日はお忙しい中お時間をいただき、誠にありがとうございました。貴社の課題やご要望を詳しく伺うことができ、大変参考になりました。次回は具体的なご提案をお持ちいたします。今後ともよろしくお願いいたします。」
目的とトーンを明示しているため、ビジネスにふさわしい表現で自然な印象になっています。
“何に感謝したいか”を具体的に書いた依頼文が、丁寧さと誠実さを引き出しています。
見積依頼・回答メール:要点を整理して正確に伝える書き方
[依頼文(プロンプト)]
「取引先に見積をお願いするメールを書いてください。希望納期と数量を明記し、返信期限も伝えたいです。社外向けの丁寧な文体でお願いします。」
[ChatGPTの生成結果]
「お世話になっております。下記内容でお見積をお願いできますでしょうか。納期は3月15日、数量は100セットを予定しております。お手数ですが、3月8日までにご回答をいただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。」
この例では、伝えるべき条件(納期・数量・期限)を整理して入力した点がポイントです。
数字や日付を具体的に伝えるだけで、生成される文の精度と信頼感が格段に上がります。
社内報告メール:トーンを柔らかくしつつ事実をまとめるコツ
[依頼文(プロンプト)]
「社内チーム向けに、展示会出展の結果を報告するメールを書いてください。来場者数や反応を簡潔にまとめ、次回への意気込みも添えてください。300文字以内で。」
[ChatGPTの生成結果]
「展示会へのご協力ありがとうございました。来場者は延べ500名を超え、多くの前向きな反応をいただきました。次回はブース内容をさらに充実させ、より多くのお客様にご紹介できるよう準備を進めます。引き続きよろしくお願いいたします。」
社内文書では過度に形式ばらず、共有の温度感を大切にした依頼文が効果的です。
「誰に向けて書くか」を意識するだけで、ChatGPTの文体が一段階自然になります。
取引先への日程調整:依頼文で“優先度”を伝えるポイント
[依頼文(プロンプト)]
「取引先との打ち合わせ日程を調整するメールを書いてください。候補日を3つ挙げ、相手の都合を最優先にするトーンで。250文字以内でお願いします。」
[ChatGPTの生成結果]
「お世話になっております。次回のお打ち合わせにつきまして、以下日程のいずれかでご都合はいかがでしょうか。①3月6日(火)午前、②3月7日(水)午後、③3月8日(木)午前。ご都合の良いお時間をお知らせいただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。」
「相手を立てるトーンで」と指示するだけで、文全体が柔らかく、圧を感じさせない調整メールになります。
AIは優先順位を示す言葉を理解するため、依頼文に一言添えることで意図が伝わりやすくなります。
お詫び・トラブル対応メール:AI任せにしない言葉選び
[依頼文(プロンプト)]
「納品遅延についてお詫びするメールを書いてください。原因を簡潔に説明し、再発防止の姿勢を伝えたいです。誠実で落ち着いた文体でお願いします。」
[ChatGPTの生成結果]
「納品が予定より遅れておりますこと、深くお詫び申し上げます。原因は部材の入荷遅延によるものであり、現在は再発防止に向けた改善を進めております。ご迷惑をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。」
謝罪メールでは、AIの出力をそのまま使うと「定型的で感情のこもらない文」になりやすい傾向があります。
依頼文の段階で「誠実に伝えたい」「改善を約束したい」といった意図を添えることで、形式的すぎない表現に調整できます。
いずれのシーンでも共通するのは、「目的・相手・トーン」を依頼文で具体的に伝えることです。ChatGPTは入力情報の解像度に応じて出力を調整するため、この3点を意識するだけで精度が大きく変わります。
生成された文を“人の言葉”に整える3つのチェックポイント
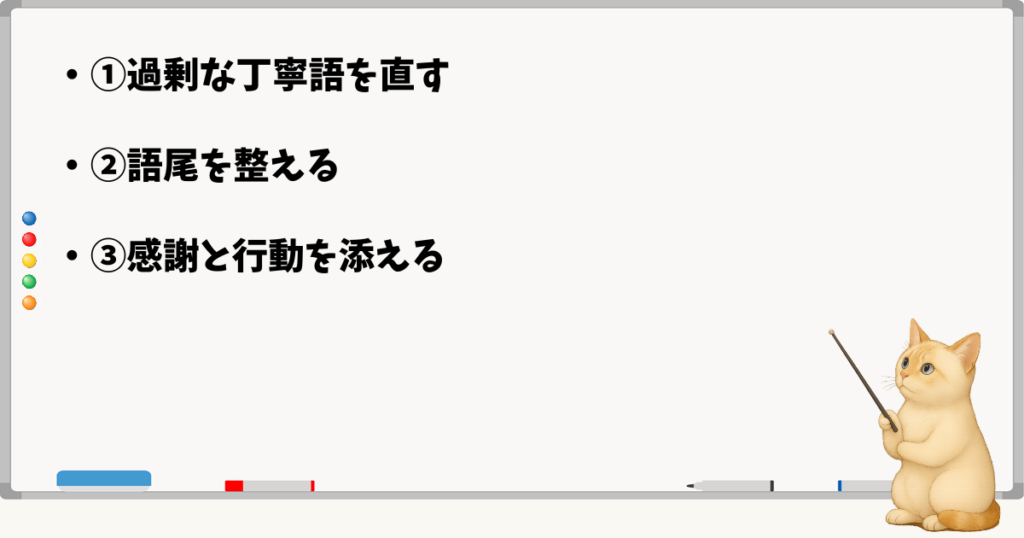
ChatGPTが作るメール文は読みやすく整っていますが、そのまま送るとどこか“機械的な印象”になることがあります。
ここからは、生成された文を実際に使う前に確認したい3つのチェックポイントを紹介します。
人が書いたような温度と流れを戻すことで、信頼感がぐっと高まります。
①過剰な丁寧語を直す:「申し上げます」の連続に注意
ChatGPTはビジネスメールにおいて安全側に倒れがちで、過剰に丁寧な表現を多用する傾向があります。
特に「〜いたします」「〜申し上げます」などが連続すると、硬すぎる印象を与えかねません。文全体の流れを見て、1通の中での重複を避けるだけでも印象が柔らかくなります。
「お礼申し上げます」「ご連絡申し上げます」を続けて使っていたら、後者を「ご連絡いたします」に変えるだけでも自然です。文意を変えずに言葉を少し崩すことが、機械感を減らす最も簡単な方法です。
また、社内文書や同僚宛てでは、「お疲れさまです」「ありがとうございます」で十分なケースもあります。
相手との距離感に合わせて、丁寧語を1段階調整する意識を持ちましょう。
②語尾を整える:連続する「〜です」「〜ます」を避ける
AIが生成した文は文末が一定のリズムで並びやすく、「〜です」「〜ます」が続くことで単調に感じられます。
人が書くメールには、文の長さや調子に変化があるものです。文末の語調を意識的に変えるだけで、驚くほど自然な印象になります。
「〜と考えております」「〜の予定です」「〜を予定しております」などの言い回しが連続したら、1文を削るか言い換えを加えます。
「〜と感じています」「〜の見込みです」などに置き換えるだけでリズムが戻ります。
また、文末が長く続く場合は、「一度ご確認ください」「ご検討をお願いいたします」など、動作で締める表現を1文加えると、読み手の印象が締まります。
③感謝と行動を添える:最後の一文で温度を戻す
AIが生成した文は文法的に完璧でも、“人の気持ち”がやや抜けていることがあります。
最後の一文に「お手数をおかけします」「いつもありがとうございます」「今後ともよろしくお願いいたします」など、感謝や行動を促す言葉を添えるだけで、ぐっと人間味が増します。
メールの締めくくりは内容よりも印象を残す部分です。AIが作った文を読んで冷たく感じたら、最後にひと呼吸置くような一文を足しましょう。
「言葉で空気を整える」という意識が、生成文を自然な人の言葉へと変えてくれます。
AIの出力を整えるのは手間ではなく“自分の声を戻す作業”です。ChatGPTが作った文を手にしたあとに、この3点をチェックするだけで、実務メールとしての完成度が一段上がります。
社内でChatGPTのメール文例を共有・活用する方法
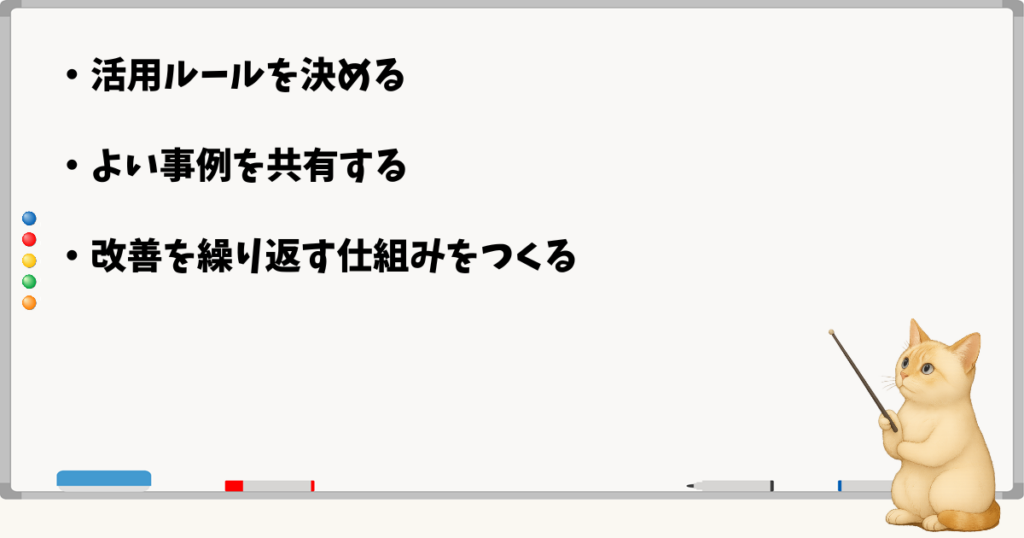
ChatGPTを使ったメール作成は、個人の効率化だけでなくチーム全体の品質を高める取り組みにもなります。
ここでは、社内で文例を共有しながら安全に活用するための3つのポイントを紹介します。
重要なのは、「正解を統一すること」ではなく、みんなで“よりよい表現”を見つけていく流れを作ることです。
活用ルールを決める:目的と扱う情報の線引きを共有する
まずは、ChatGPTをどの範囲で使うかを社内で明確にしておくことが大切です。
ビジネスメールの下書きや構成づくりなど、目的を定めた上で使えば安全で効果的なツールになります。
逆に、顧客情報や機密性の高い内容を直接入力すると、情報漏えいのリスクにつながる可能性があります。
「文面の型を作るための利用に限定する」「社外メールは最終的に人の確認を経て送信する」など、使用範囲をあらかじめ線引きしておくと安心です。
ルールがあることでチーム全員が同じ基準で活用でき、トラブルを防げます。
よい事例を共有する:成功体験をナレッジ化する
ChatGPTを業務に取り入れると、「思ったより自然に書けた」成功体験が必ず生まれます。
そのときは個人の成果で終わらせず、社内チャットや共有フォルダなどに依頼文と結果のセットを残しておきましょう。
実際に使われたプロンプトをもとに共有することで、他のメンバーも同じ品質のメールを作りやすくなります。
また、「この言い回しは顧客に好評だった」「このトーンだと柔らかく伝わった」など、フィードバックを添えて蓄積していくことも有効です。
ナレッジ共有は単なる文例集ではなく、チーム全体の“言葉の感度”を育てる取り組みになります。
改善を繰り返す仕組みをつくる:AIと人の共同編集を前提に
メール文例の共有は、完成品を集めることが目的ではありません。
AIと人が共同で改善していくプロセスを仕組みにすることが大切です。
たとえば「毎月1回、AI活用のふりかえりを行う」「よく使うプロンプトを定期的に見直す」など、小さな習慣化から始めてみましょう。
社内で共有された文例は次にAIへ渡す“学習素材”にもなります。
過去の文例をもとに「このパターンを少し柔らかくして」と指示すれば、より精度の高いメール文が生成できます。
人が整えた文をAIが学び、AIが作った文を人が磨く。この往復が続くことで、組織全体の言葉の質が少しずつ上がっていきます。
共有はゴールではなく育てる仕組みです。ChatGPTを“文章を考えるきっかけ”として扱うことで、社員一人ひとりが言葉に意識を持ち、より伝わるコミュニケーションへと変化していきます。
まとめ:ChatGPTを使う目的は“文章を通じて人に伝えること”
ここまで、ChatGPTでメールを作るときの流れを見てきました。
目的を整理し、構成を考え、適切なプロンプトで依頼し、生成された文を人の言葉に整える。 どのステップも、最終的には“相手に伝わる言葉を選ぶ”ための作業です。
AIを活用すると、文を整えるスピードや正確さは大きく向上します。
しかし、どんなに自然な文が出力されても、「何を、どんな気持ちで伝えたいか」を考える部分は人にしかできません。 ChatGPTはその思考を言葉にする手助けをしてくれる道具です。
メールを自動で作ることが目的ではなく、伝える力を高めるプロセスを共有することこそがAI活用の価値だといえます。 社
内で文例を共有し合うことで、表現の引き出しが増え、社員一人ひとりの言葉が磨かれていきます。
AIに任せるのではなく、AIと一緒に考える。 その意識を持つだけで、メールはより誠実で温かいものになります。 ChatGPTを使う目的は、最終的に“人に伝える力を育てること”なのです。
もし「自社でも試してみたい」「どの業務から導入すればよいか迷っている」と感じたら、 私たちCreamCodeがサポートします。
ChatGPTを安全かつ効果的に使う仕組みを、 現場に合わせて一緒に整えていきましょう。小さな相談からでも大丈夫です。

