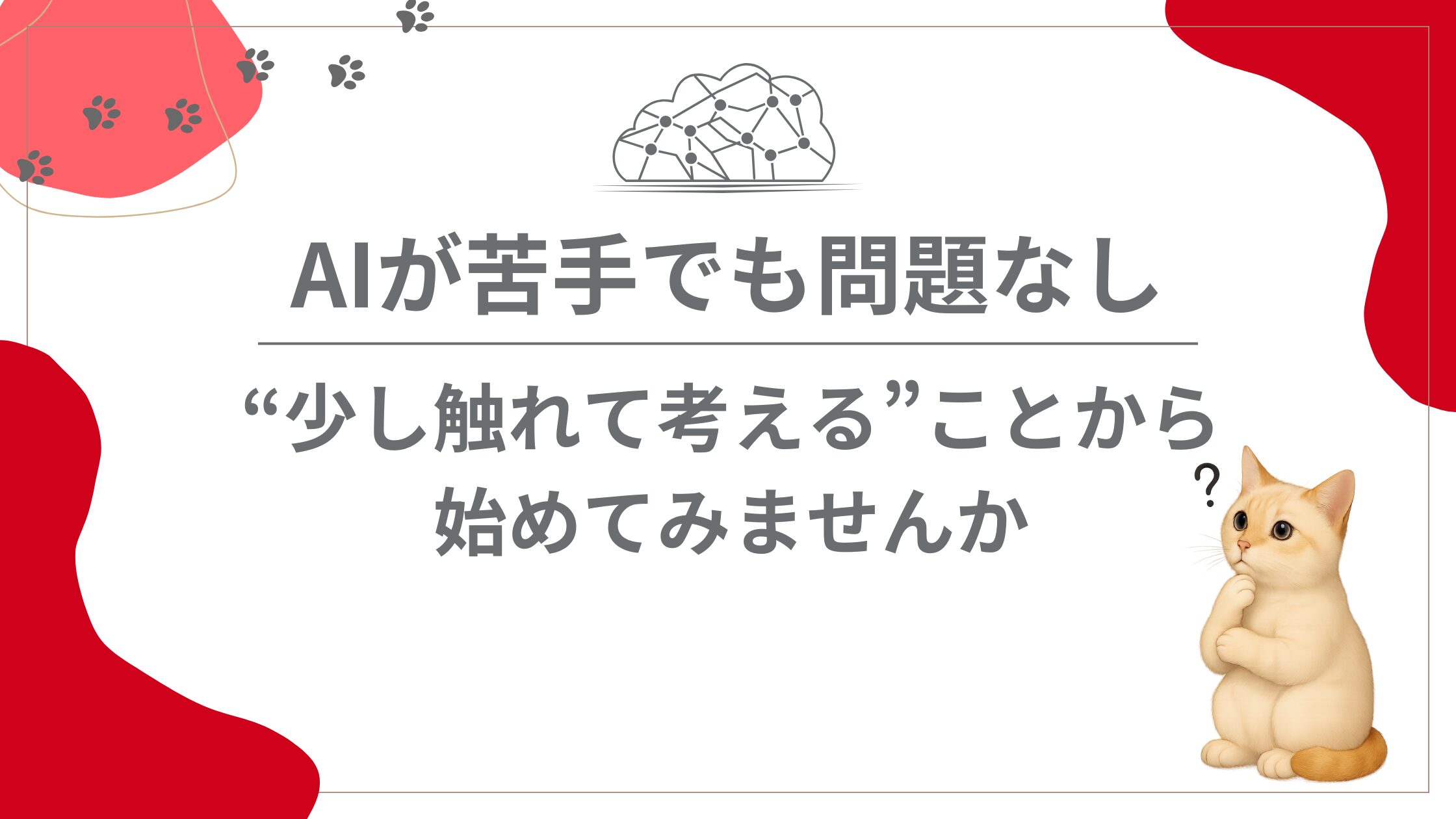「正直、AIってよく分からない」。そう感じている経営者の方は少なくありません。
会議や商談で“AI活用”という言葉が飛び交うたびに、「自分も何かしなければ」と焦りを覚える——そんな声を、大垣の企業でもよく聞きます。
でも、本当はそれでいいのです。AIは“詳しい人”が動かせばいい道具ではなく、“方向を示す人”がどう関わるかで価値が決まるもの。経営者に求められるのは操作のスキルではなく、「会社としてどう向き合うか」という判断です。
この記事では、AIが苦手なままでも一歩を踏み出せる考え方をまとめました。
焦らず、比べず、まず“少し触れて考える”。その積み重ねが、AI時代の経営を支える力になります。
「苦手なまま」でも大丈夫。AIは“向き合い方”が9割
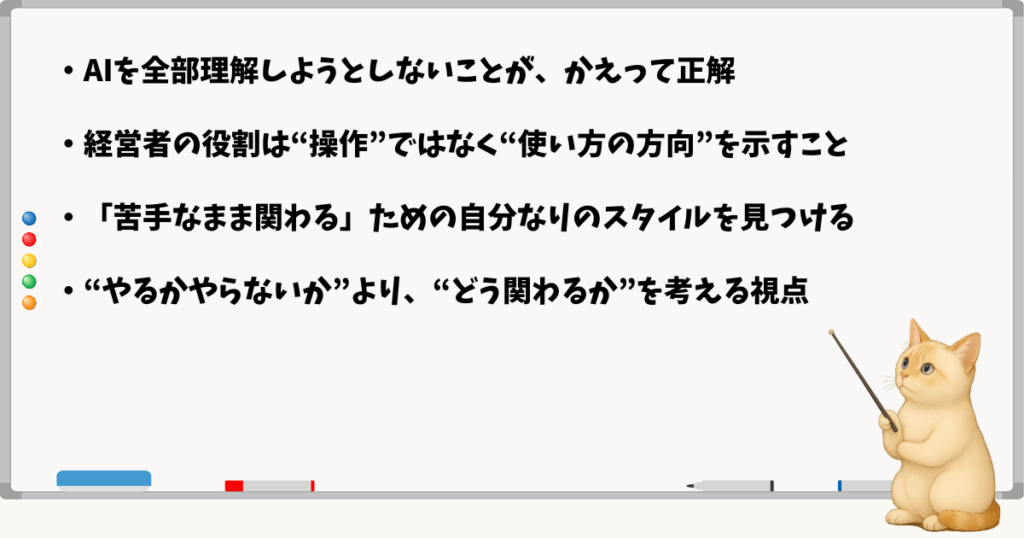
「苦手なまま」でも大丈夫。AIは“向き合い方”が9割
AIを全部理解しようとしないことが、かえって正解
経営者の時間は限られています。AIの仕組みや用語を細かく覚えるよりも、判断に必要な範囲だけ理解するほうが現実的です。
たとえば「要約は得意」「社外秘は入れない」。この程度の理解でも十分動けます。
完璧を目指すほど判断が遅れます。AIは使いながら分かるものです。最初から“分からない前提”で取り組むほうが冷静さを保てます。
まずは三つの軸だけ意識しましょう。
①入力してよい情報の範囲
②得意・不得意の目安
③試すときの小さな手順
これで多くの意思決定は足ります。
経営者の役割は“操作”ではなく“使い方の方向”を示すこと
経営者が担うのは作業ではなく、「この会社でAIを何に使うか」を決めることです。方向を示せば、社員は安心して試せます。
業務を三層に分けると考えやすいです。売上に直結する仕事、品質を守る仕事、定型事務。
このうち時間を多く使っている層を見つけ、「まず定型作業の負担を減らす」と決める。それだけで動き出します。
ルールは簡単で構いません。「お客様情報は入力しない」「結果は定期共有」「迷ったら止めて相談」。この三点があれば十分です。
操作の話に傾いたときは、「目的は?」「成果の基準は?」と軸を戻すだけで会議の空気が変わります。
「苦手なまま関わる」ための自分なりのスタイルを見つける
AIと距離を取りすぎても近づきすぎても続きません。まずは、自分に合う“関わり方の型”を一つ決めることです。
たとえば「週1回10分触る」「議事録の要約だけ使う」。決めておくと迷いが減り、続きます。
もう一つは「誰と関わるか」。社内の得意な人や外部の相談相手を決めておくと、質問が溜まらず前に進めます。
そして「どこで線を引くか」。たとえば「下書きには使うが最終稿は人が整える」。線があるだけで安心できます。
スタイルは完璧でなくて構いません。まず決めて、やりながら調整すればよいのです。苦手でも形があれば関わり続けられます。
“やるかやらないか”より、“どう関わるか”を考える視点
AIは白黒で決めるものではありません。どの距離で、どの業務に、どんなルールで関わるかを考えることが大切です。
近すぎると混乱し、遠すぎると置いていかれます。中間が心地よい距離です。
考えるときは三つの視点を持ちましょう。
①目的:何の負担を減らしたいか
②範囲:どこまでAIに任せるか
③検証:結果をどう比べるか
この3点があれば方向がぶれません。
まずは小さく試す。「企画書の骨子だけAIに出させ、人が肉付けする」。これで十分です。効果が薄い領域はあえて外すのも判断です。
関わり方を決めると、会話が「できる・できない」から「どこまで・どう試す」に変わります。苦手でも、向き合い方が整っていれば会社は進みます。
焦らなくていい理由。経営者が知るべきことはほんの少し
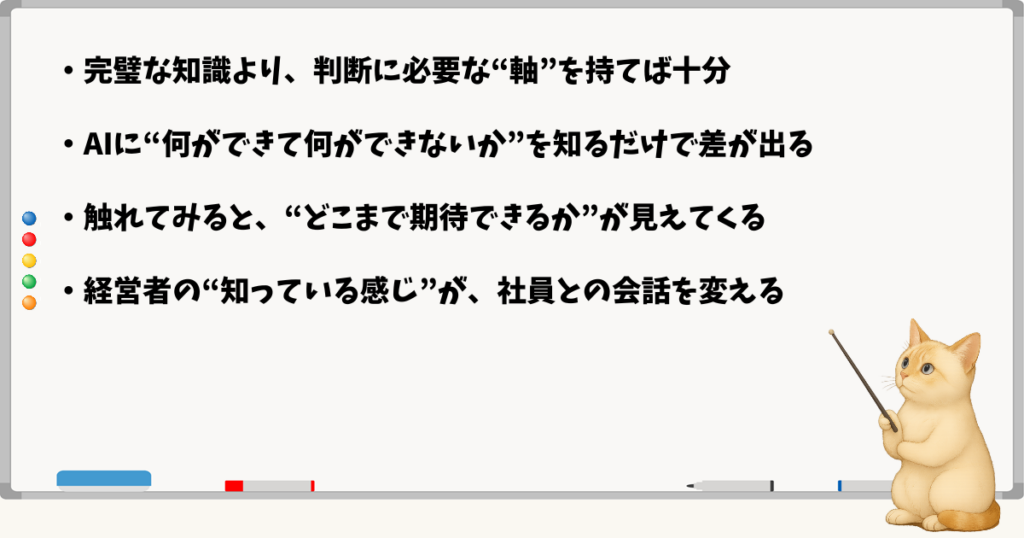
完璧な知識より、判断に必要な“軸”を持てば十分
AIは日々進化しており、すべてを理解し続けるのは現実的ではありません。大切なのは、情報の量ではなく判断の軸を自分の中に持つことです。
たとえば「AIに任せる目的は業務効率化」「社外秘は絶対に扱わない」など、2〜3の基準を明確にするだけで方向はぶれません。
判断の軸を持つと、他人の意見に振り回されにくくなります。「うちには関係ない」「まだ早い」と感じた時も、軸をもとに判断すれば納得感があります。
経営の現場では、正解よりも“納得できる選択”の方が長続きします。
特にAIのような技術分野では誰もが初めての経験です。
「自社では何を優先するか」を明確にできる経営者ほど、次の手を落ち着いて選べます。完璧な知識ではなく、“選び方の基準”が会社を守ります。
AIに“何ができて何ができないか”を知るだけで差が出る
AIにできることは確かに増えていますが、万能ではありません。
得意なのは文章の整理や要約、アイデアの提示など、言葉に関わる作業。逆に苦手なのは、数値の精密計算や現場判断のような、人の文脈が必要な領域です。
この大枠を知っておくだけで社内の会話が変わります。社員が提案してきたときに「それはAIに合うね」「これはまだ人の確認が要るね」と整理できる。わずか数秒の判断でも、プロジェクトの方向が整います。
つまり、AIの専門知識を深く持つ必要はありません。大切なのは“人とAIの棲み分け”を理解すること。これができれば、苦手でも十分戦えます。
触れてみると、“どこまで期待できるか”が見えてくる
AIを理解する最短の方法は実際に少し触ってみることです。
1時間の研修より10分の体験のほうが印象に残ります。たとえば「文章を短くして」と打ってみるだけで、どんな返答が返るか、感覚で分かります。
触れることで、AIの得意な場面と苦手な場面が体で分かります。「ここは助かる」「ここはまだ難しい」と体感すれば、期待値を自然に調整できます。結果として“無理のない導入”ができます。
経営者自身が体験すると社内の雰囲気も変わります。
社員が「社長も触ったんだ」と感じるだけで、安心感が広がるのです。大切なのは、理解よりも体験。触れることが一番の学びになります。
経営者の“知っている感じ”が、社員との会話を変える
AIを詳しく説明できなくても、「どんなことができるらしい」という“知っている感じ”があるだけで、社員との会話がスムーズになります。
経営者が少しでも理解していると、現場の不安が和らぐのです。
社員がAIを提案してきたとき。「どんな場面で使えそう?」「安全面は確認した?」と軽く問いかけるだけで対話が始まります。完璧な質問でなくても構いません。“興味を持って聞く姿勢”が、何よりのメッセージです。
その積み重ねが社内の空気を変えます。AIの話題が日常会話に混ざり始めると、自然と小さな改善が動き出します。経営者の“知っている感じ”は、知識ではなく、社内の風通しを良くする鍵なのです。
社員や周囲にどう向き合えばいいか。質問の仕方がポイント
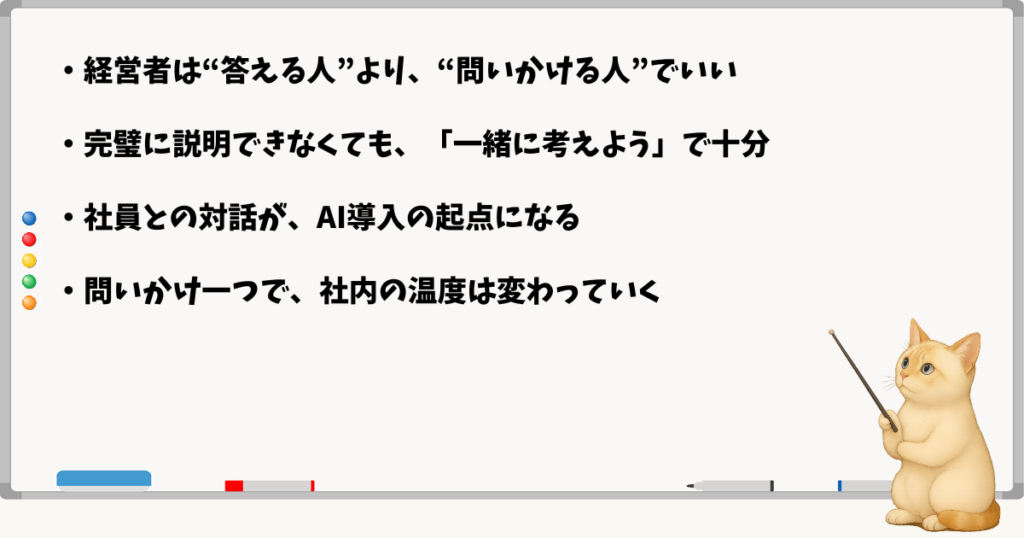
社員や周囲にどう向き合えばいいか。質問の仕方がポイント
経営者は“答える人”より、“問いかける人”でいい
AIの専門家である必要はありません。経営者の役割は答えを持つことより、「何を考えるべきか」を見つける問いを立てることです。
問いを示すだけで、社内の会話は自然と前へ動きます。
「この作業、AIで軽くできる部分はある?」「使うとしたらどこが心配?」と尋ねるだけで、社員の思考が動き始めます。経営者が“聞く側”にまわると、現場の知恵が上がってくるのです。
答えを急がない姿勢が、結果として最良の判断を導きます。問いがある組織は、常に考え続ける力を持ちます。
「一緒に考える」から「一緒に動く」へ少しずつ進める
AIの話題は最初から説明しようとせず、共に動くきっかけをつくることが大切です。
「自分も分からないけど試してみよう」と声をかけると、社員は安心して参加できます。
最初は雑談レベルでも構いません。「AIにこれ頼んでみたら?」といった軽いやりとりが行動の始まりです。知識の共有よりも、試す時間を共有するほうが実務に近づきます。
「一緒に考える」関係から「一緒に動く」関係へ。その過程で、経営者も自然と理解が深まります。説明できるようになるのは後で十分です。
社員との対話が、AI導入の起点になる
AI導入の第一歩は会議でもマニュアルでもなく「日常の会話」です。「どの作業が面倒?」「どんなときに時間を取られている?」と話すだけで、導入の方向が見えてきます。
営業報告や文書作成など日常に潜む「小さな負担」をテーマにすると、社員も話しやすくなります。AIの話をしているつもりがなくても、それがすでに導入の準備です。
会話を重ねると、「これなら試せそう」「自分がやってみたい」といった前向きな声が生まれます。対話こそが実質的なスタートラインです。
問いかけ一つで、社内の温度は変わっていく
経営者の一言が、社内の空気を変えることがあります。「もしAIが使えるなら、何を任せたい?」「どんな作業が減ると助かる?」。このような問いは、社員の発想を刺激します。
問いが増えるほど、社員は自分たちの課題を“自分ごと”として考えるようになります。それが、AI導入だけでなく業務改善全体に波及します。
正解を求めすぎず、問いを重ねること。それが“考える組織”を育てる道です。経営者の問いが続く限り、会社は進化し続けます。
“得意じゃなくてもできる関わり方”という視点
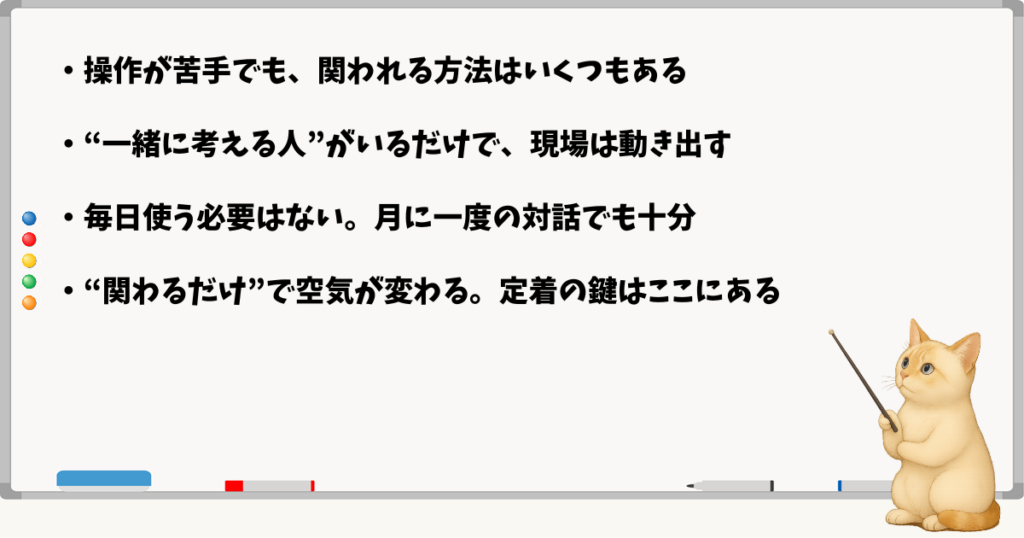
操作が苦手でも、関われる方法はいくつもある
AI活用と聞くと「自分が操作できなければ意味がない」と考えがちです。
しかし実際には、経営者が直接使わなくても社内は動かせます。社員がAIで作った資料を確認し、良い点を見つけてフィードバックするだけでも立派な関わり方です。
他にも「この作業にAIを使ってみて」と方向を出す、あるいは「リスクを洗い出しておこう」と声をかけることも経営の役割です。AIの運用には、必ず“方針”と“見守り役”が必要です。それを担えるのは経営者しかいません。
つまり、使う人ではなく、使う環境を整える人になる。これが“苦手でもできる”最初の関わり方です。
操作が得意な人を生かすことで、組織全体が動き始めます。
“一緒に考える人”がいるだけで、現場は動き出す
AI活用を進めるうえで、経営者が孤立すると止まりがちです。重要なのは、一緒に考える人を持つこと。社内でも外部でも構いません。話せる相手がいるだけで、考えが整理されます。
たとえば、社内では「AI推進チーム」を名乗る2〜3人を決める。全員が専門家である必要はなく、「試して報告する係」「情報をまとめる係」など、役割を分けて始めます。
外部であれば、地域の商工会やIT支援の専門家に話を聞くだけでも構いません。大垣周辺でも、小規模事業者を対象にしたAI相談会が増えています。人と話すことで、孤独な“学び”が“共有”に変わります。
経営者が一人で抱えず、考える時間を共有すること。それだけで前進のスピードは変わります。
毎日使う必要はない。月に一度の対話でも十分
AIは「毎日使わなければ身につかない」という性質のものではありません。むしろ、月に一度でも“話題に上る”状態を保つことが大切です。それだけで組織の中に“AIを考える習慣”が根づきます。
月例会議の最後に5分だけ、「最近AIで試したことある?」と聞く。それだけでOKです。社員が発言し、誰かが共感すれば、それが社内学習になります。
使う頻度よりも、思い出す頻度。定期的に話題に出ることで、AIは会社の“自然な道具”になります。続けるコツは、無理にスケジュール化しないことです。自然に出る会話が一番長続きします。
“関わるだけ”で空気が変わる。定着の鍵はここにある
経営者がAIを話題にするだけで、会社の空気は変わります。社員は「興味を持ってくれている」と感じ、挑戦しやすくなります。これは技術教育よりも大きな効果があります。
AI導入がうまく進む会社には共通点があります。それは「経営者がAIを日常会話に混ぜている」こと。使い方を指示するのではなく、「こんなニュースがあったね」「うちでもできるかな」と投げかけるだけで十分です。
AIを“語れる話題”にする。それが定着の最初の一歩です。関わり方の巧拙より、話題にできる温度が重要です。
経営者が関わり続ける姿勢そのものが、社内の安心感になります。
今日できる一歩。“AIって何ができるの?”と聞いてみる
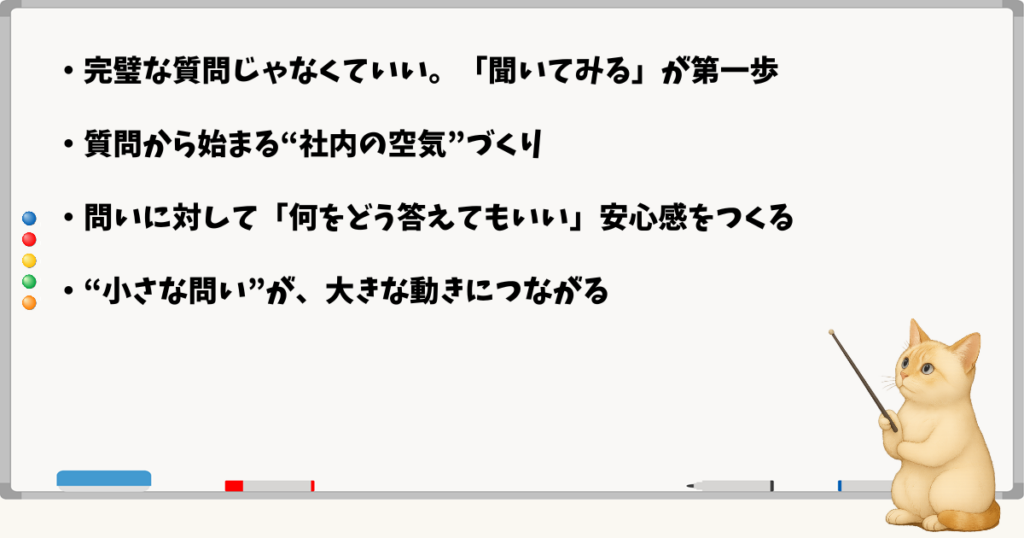
完璧な質問じゃなくていい。「聞いてみる」が第一歩
AIに関する最初の行動は勉強でも導入でもありません。
「AIって何ができるの?」と誰かに聞いてみることです。この一言が、すでに最初の一歩です。
質問は完璧でなくて構いません。むしろ漠然としている方が、相手が説明しやすくなります。「うちでも使える?」「安全なの?」そんな素朴な疑問こそ、自然な対話のきっかけです。
AIの話題は知っている人にしか聞けないわけではありません。社内の若手や、別業界の知人に聞いても良いのです。“聞ける関係”があることが、AI時代の強みになります。
質問から始まる“社内の空気”づくり
経営者が質問する姿は、社内に「聞いていい雰囲気」を生みます。社員も「分からないことを聞いていいんだ」と感じ、意見を出しやすくなります。
会議の冒頭に「最近AIって使ってみた?」と聞くだけでも空気は柔らかくなります。問いが社内に広がると、挑戦の文化が育つのです。
この“空気づくり”こそ、経営者にしかできない関わり方です。答えを出すのではなく、考える場を整える。AI導入は、そんな雰囲気づくりから始まります。
問いに対して「何をどう答えてもいい」安心感をつくる
質問したとき、社員がすぐに答えられなくても大丈夫です。大切なのは、「どんな答えでも受け止める姿勢」です。「面白いね」「その考えもあるね」と返すだけで、社員の意欲が続きます。
AIの導入がうまく進まない会社は、「間違えたら怒られる」空気があるところです。逆に、どんな意見でも受け止められる環境では、自然と挑戦が増えます。安心感が、創造の土台になります。
経営者の一言が社員にとっての「試してみても大丈夫」というサインになります。AIの成功は、まずこのサインを出せるかどうかで決まります。
“小さな問い”が、大きな動きにつながる
たった一つの問いが、会社の未来を動かすことがあります。「これ、AIでできる?」という一言から、新しい仕組みが生まれることも少なくありません。
重要なのは、「大きな決断」ではなく「小さな問い」を続けることです。続けるうちに、気づけば会社全体が“考える組織”に変わっています。
今日できる一歩は、ほんの一言の問いかけです。AIに詳しくなるよりも、AIを話題にできる場を増やす。それが、苦手なままでも前に進むための最初のアクションです。
まとめ:苦手でも「向き合う姿勢」があれば、もう十分です
AIを理解しきる必要はありません。経営者に求められるのは、理解よりも“向き合う姿勢”です。
分からないことを受け入れ、考えながら進める。その柔らかさが、組織の新しい力になります。
焦る必要も完璧を目指す必要もありません。少し触れて考え、社員と話し、問いを重ねていく。それだけで会社は確実に変わっていきます。
AIは「導入するもの」ではなく「話題にできる関係」から始まります。経営者が関心を持ち、社内に温度を生むことが、最初で最大の一歩です。
あなたの会社にも、もうすでに始められることがあります。“AIって何ができるの?”と一度、誰かに聞いてみてください。それが、変化の起点になります。
「AIが苦手でも大丈夫」——まずは話して整理してみませんか?
私たちCreamCodeでは、岐阜・大垣エリアの中小企業の皆さまと一緒に、“無理なくAIと関わる方法”を考えています。導入の話ではなく、「そもそも何から考えればいいか」を一緒に整理する時間です。
専門用語はいりません。経営の視点から、現場の声を聞きながら、貴社に合った“関わり方”を見つけましょう。▶ 無料相談・お問い合わせはこちら